「家に帰る(帰す)」を目標に、歩みを重ねてきた日々。その途上で訪れる突然の別れは、職員にとってもご家族にとっても、静かに大きな波となって押し寄せます。
つい昨日までの笑顔が残る場所で
最近、私の職場では突然のお別れが続いています。皆さま100歳に近いご高齢で、「仕方のないところもある」と頭では分かっていても、心は追いつかないことがあります。
リハビリは「家に帰る(帰す)」つもりで取り組むからこそ、別れの重さも増します。担当でなくても胸が詰まるのに、担当者の辛さは計り知れません。
当日は気が張っていても、あとからじわじわと喪失感がやってくる──
「あぁ、もうここでお食事をされることはないんだな」
「ここで立つ練習をしていたよな」
「お子さん達が『早く家に帰れるように、リハビリ頑張って』って言っていたな」
キューブラー・ロスの「死の受容」を思い出す
学生の頃に学んだ、キューブラー・ロスの死の受容の5段階を思い出します。これは、人が死に直面したときに経験しうる心理過程を示したものです(順番通りに進むとは限らず、行き来もあります)。
- 否認:自分に起きている現実を受け入れられない。
- 怒り:なぜ自分が──という怒りや不満が向かう。
- 取引:神や運命に「もう少しだけ」と交渉しようとする。
- 抑うつ:取引が叶わないと悟り、深い悲しみや無力感に包まれる。
- 受容:静かに現実を受け入れ、心に安寧が訪れる。
ご本人だけでなく、ご家族もまた、いまどこかの段階にいるのかもしれません。私たち職員は専門職である前に一人の人間として、その揺れに触れながら共に時間を過ごしています。
ご家族への敬意と祈り
私の勤務する老健では、働きながらも面会に足を運ぶご家族が本当に多く、頭の下がる思いです。忙しさの中で顔を見せ、声をかけ、手を握る──その一つひとつが、どれほどご本人の力になっていたかを思います。
「やり切った」と感じられますように。悲しみが少しずつ形を変え、穏やかな記憶へとほどけていきますように。心から祈っています。
ケアをする側の心を守る、小さな習慣
- ミニ・デブリーフ:その日のうちに3分だけ、気づきと感情をメモに残す。
- 同僚への一声:「今日はありがとう」「辛かったね」を言葉にする。
- 儀式化:ベッドサイドを整え、お茶や花をそっと置くなど、自分なりの区切りを作る。
- 身体をほぐす:深呼吸、肩回し、短い散歩。まずは身体から。
- 必要な相談:溜め込まず、上長・同僚・専門窓口へ早めにシェア。
「感じないようにする」よりも、「感じた自分を大切にする」。それが、明日のケアの力になります。
明日も、「家に帰る」を胸に
喪失感は、私たちが本気で関わってきた証でもあります。
その痛みと優しさをたずさえて、明日もまた「家に帰る」という希望に向けて、ひとつずつ積み重ねていきたいと思います。
※本記事は、老健のリハビリ現場で日々感じることの記録です。個人の体験に基づく内容であり、全ての場面に当てはまるわけではありません。
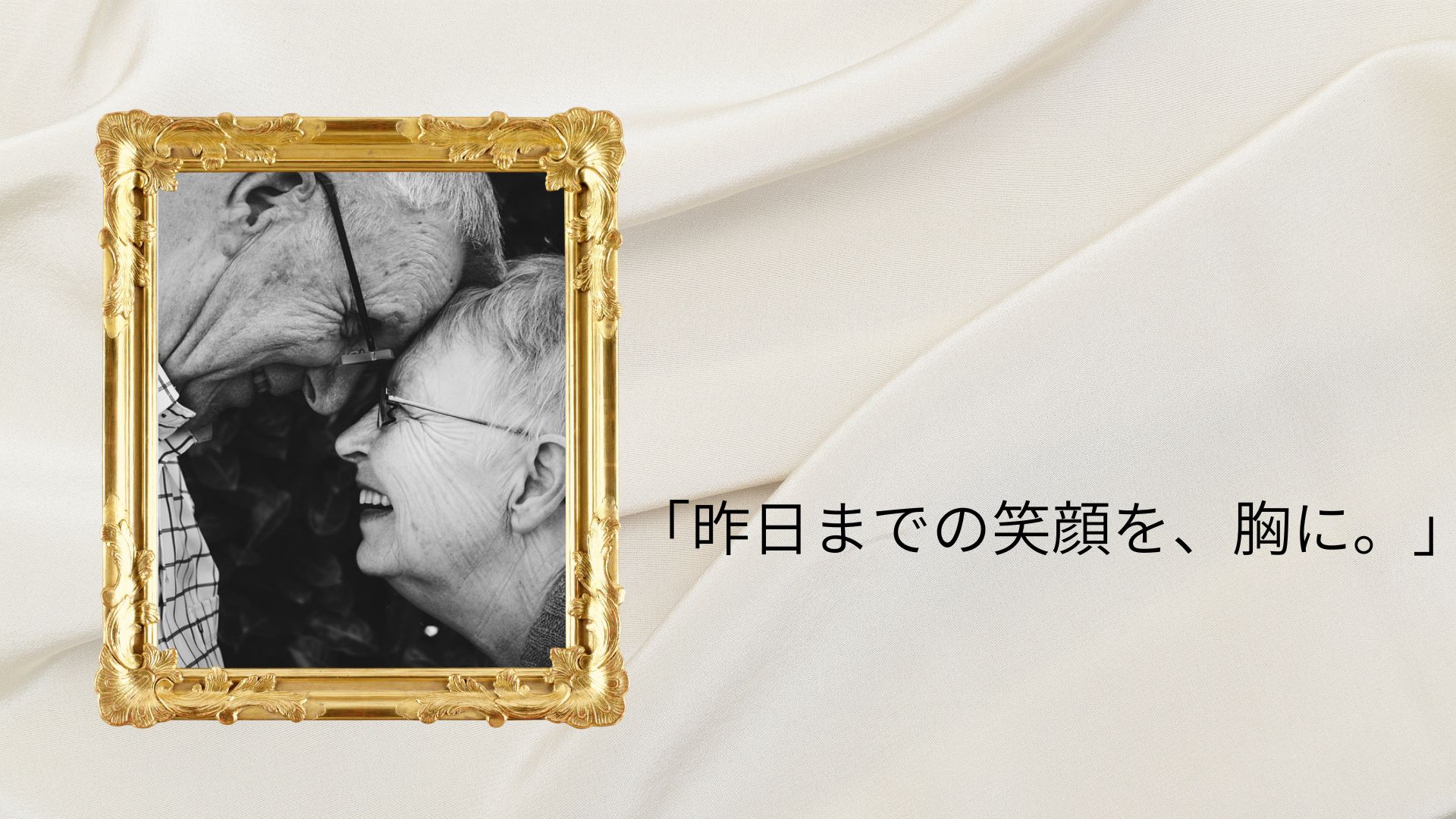


コメント