退所してデイに通所中の利用者さん。先日いらしたら、なんと左手が包帯でぐるぐる巻きになっているじゃないですか!?
「何したんだい?」と聞くと、「コンビニに買い物に行って、転んじゃったの」とのこと。どうやら左手にヒビが入ってしまったようです。
「杖、持たずに出ちゃったの」
よくよく話を聞くと、杖を持たずに出かけてしまったとか。うーん……。ときどきふらつくから、やっぱり杖は持ってほしいんですよね。
でも思い出しました。入所中も、夜な夜な職員に隠れて歩く練習をしていたことを。
同室の方がこっそり教えてくれたのです。
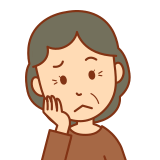
あの人、車椅子じゃなくて、歩いてトイレ行ってるわよ。廊下に誰もいないの確認してから、さぁーって歩いていってるの。
――まぁ、そんな彼女ですから、今回もちょっと冒険してしまったのでしょう。利き手の右手じゃなかったのが、せめてもの救いでした。
“歩ける”と“安全に歩ける”は別のスキル
リハビリを頑張って「歩けるようになった」人ほど、“できる自分”を確かめたくなる気持ち、よく分かります。
でも、歩ける=安全に歩けるとは限りません。特に屋外・買い物・段差・混雑などは、屋内歩行より難易度が上がります。
今日からできる:杖の「習慣化」チェック
- 玄関フックに杖の定位置を作る(靴・鍵とセット)
- 外出チェックリスト:鍵・財布・携帯・杖を声に出して確認
- バッグに折りたたみ杖を常に一本(スペアの発想)
- 買い物は時間帯を選ぶ:空いている時間に短時間で
- 段差・暗がり回避:明るい道、エレベーター優先
スタッフ目線のひと工夫
デイでは毎日顔を合わせるからこそ、「声かけ一つ」で行動が変わります。
転倒予防のための杖習慣を自然に促すには、こんな工夫が効果的です。
- 🌼 送迎車から降りるとき
「杖、ここに置いておきますね」ではなく、
→ 「降りたらまず杖を持ちましょうね。一緒に確認しますね」 - 🍵 ホールへの移動時
「転ばないように気をつけて」よりも、
→ 「この廊下、少し滑りやすいので杖ついてゆっくり行きましょう」 - 🥄 トイレ誘導のとき
「大丈夫ですか?」ではなく、
→ 「杖持っていきましょう。入り口で私が受け取りますね」 - 🧺 活動参加のとき
「歩けるから大丈夫ですよね」ではなく、
→ 「杖があると安心ですから、そばに置いておきましょう」 - 👋 帰り際の声かけ
「忘れ物ないですか?」よりも、
→ 「荷物はこちらで持つので、杖をついてしっかり歩いてください」
こうした声かけを積み重ねることで、「杖=安心の相棒」というイメージが自然と定着します。
できることを奪わずに、そっと安全を添える――それがデイでのリハビリの醍醐味かもしれません。
まとめ:その人らしさを守るための「杖」
冒険心は、その方の意欲や生きる力の表れ。だからこそ、杖という小さな工夫で“大きなリスク”を下げるのが私たちの役目だと思います。
次の外出は、杖といっしょに、また安全に。
本記事は個人の経験に基づく記録です。医療的判断が必要な場合は、主治医・専門職にご相談ください。
<おすすめ介護用品>
杖を忘れて出掛けないように、これで杖が立て掛けやすくなります。

ユーワ 杖の転倒防止器 転ばぬ杖 N ノーマル (紐無) Mサイズ

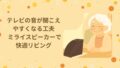

コメント