友達のお父さんが入院中です。
骨折して人工股関節の手術を終えたばかり。退院期限も迫っていて、次の居場所をどうするか…そんなお話を聞きました。
お父さんは透析をしていて、週3回は病院へ通わなければいけません。雨の日も、雪の日も、真夏の炎天下でも。もし透析がなければ、訪問リハビリを利用して、ゆっくり自宅で体力を取り戻すこともできたはず。でも透析があると、外出はどうしても避けられないのです。
家の事情
玄関には段差が2段。
今の筋力ではそこを上がるのも難しい。
お母さんも病気を抱えていて、体は思うように動かず、認知も進んできているそうです。これまではお父さんが家事も食事も担ってきたのに、入院をきっかけにそのバランスが崩れてしまった。友達自身も仕事で忙しく、両親をフルサポートするのは現実的ではありません。
老健は受け入れできる?
「じゃあ老健(介護老人保健施設)に」と考えるのが自然ですが、透析患者さんを受け入れる老健は本当に少ないんです。
理由は単純。
透析には医療体制が必須だから。
透析室を併設していたり、近隣病院と強い連携がある「病院併設型の老健」でないと、まず難しいのです。
考えられる選択肢
- 病院併設老健に入所してリハ+透析
- 透析対応可能な病院で、回復期リハ病棟をもう少し延長して過ごす
- 在宅復帰して住宅改修+訪問リハ+透析送迎をフル活用(ただし家族負担大)
- 特養や有料老人ホームで生活しつつ、透析には通院
どれも一長一短。特に「家に帰したい」という気持ちと「透析がある」という現実の間で、答えを出すのは簡単ではありません。
日本の透析の現実
日本では腎移植はまだ一般的ではなく、透析が当たり前の選択肢。
透析をやめる=数週間以内に死を迎える、という厳しい現実もあります。
だからこそ、透析を受けながら「どう生きていくか」を考え続けなければならないんですよね。
まとめ
友達は「できることなら自宅へ」と願っています。でも、透析があると生活の選択肢が大きく制限されます。現実的には、病院併設の老健を探すことが一番安全で安心。そこから、段差の改修や在宅支援サービスを組み合わせて、少しずつ自宅復帰を目指すのがよいのかもしれません。
👉 透析と老健、在宅復帰。
簡単ではないけれど、「本人が安心して生活できる場所」をどう作っていくか。その話し合いこそが、今の日本の高齢社会にとても大切なことなんだと思いました。
もっと知りたい方へ
透析と「どう生きるか/どう支えるか」を考えるときに役立つ本を選びました。
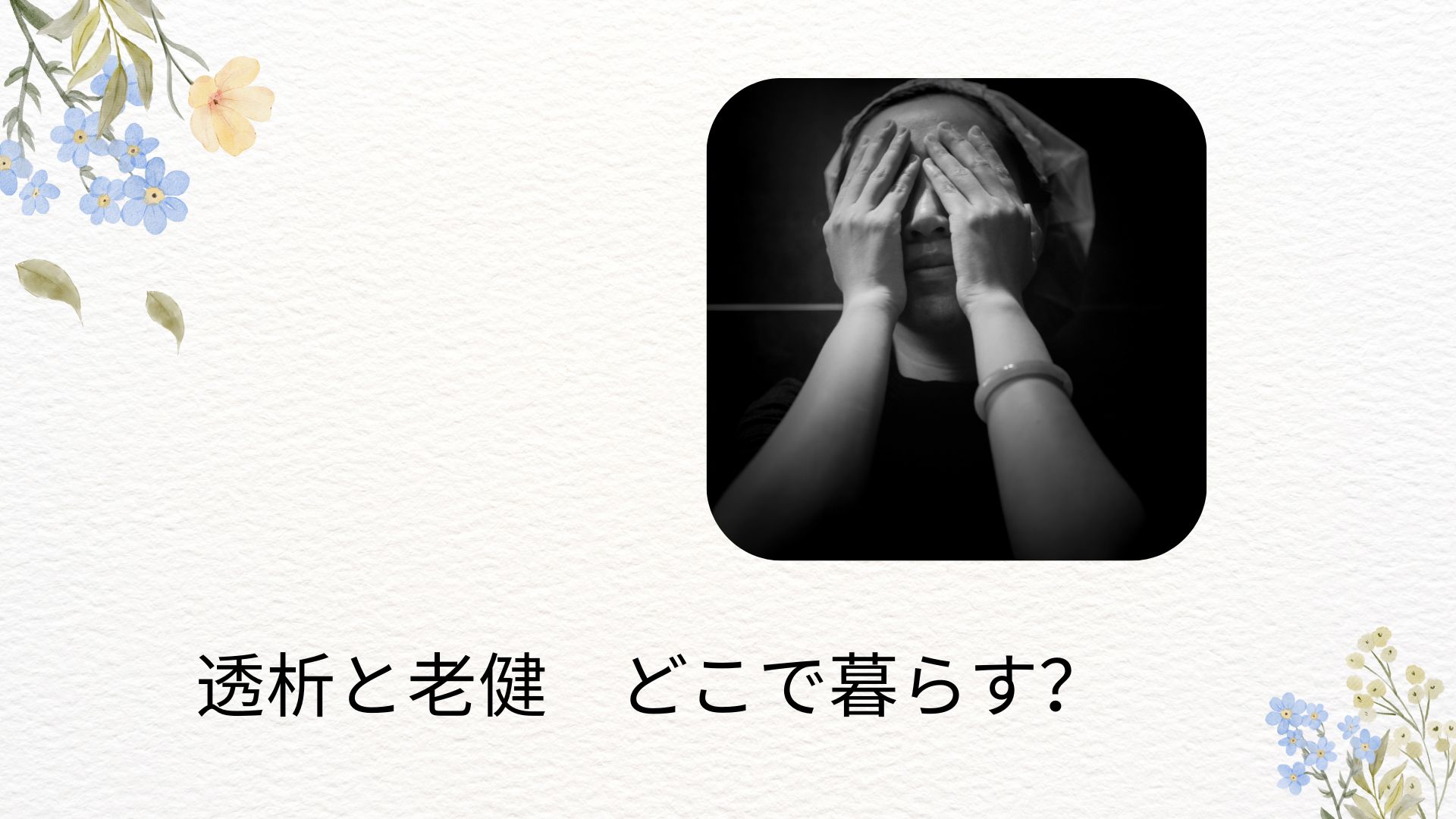


コメント