病院でもなく、特養でもない。「老健」=老人保健施設って、実はあまり知られていない存在かもしれません。今回は、理学療法士である私ポテチが、実際に老健で働いて感じた「本当の役割」についてお話しします。
老健は「病院と在宅の中間」にある場所
老健は、入院していた高齢者がすぐ自宅に戻れないときに、一時的に入所してリハビリや生活訓練を受けるための施設です。
医療処置は限定的ですが、医師・看護師・リハ職・介護職など多職種が連携して、「在宅復帰」をサポートします。
介護保険で運営されている施設
老健は医療保険ではなく介護保険で成り立っている施設です。
そのため、病院のように医療行為を自由に行えるわけではありません。入所中に医療機関を受診すると、施設側に金銭的な持ち出しが発生するため、基本的には入所時に持参された薬や市販薬で対応することも多くなります。
リハビリと生活支援が中心
リハビリテーションの提供も、老健の大きな特徴です。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がチームでかかわり、自宅で再び暮らせるための「生活に直結するリハビリ」を提供します。
トイレ動作や更衣、階段昇降など、病院では十分に取り組めなかった「生活動作」こそが、ここでは主役になります。
「終の住処」ではないけれど…
老健の目的は「在宅復帰」ですが、実際には自宅に戻れず、長期間の入所や、次の施設へのつなぎとして使われることもあります。
例:自宅 → 入院 → 老健 → 特養 or グループホーム
その人の状態や家族の事情によって、様々なパターンが存在します。
現場にいても、知らなかった
正直、私も老健に勤めるまでは「お年寄りが集まるところ」くらいの認識しかありませんでした。
実際には、医療と生活支援、介護とリハビリが交差する現場であり、スタッフに求められるスキルも幅広いです。
病院よりも生活に近く、特養よりも医療に近い――
それが老健という施設の特徴だと、今では感じています。
医療に「かかれない」現実と経営の苦悩
体調を崩したときにすぐ病院へ――というわけにはいきません。
老健では外部の医療にかかると施設の持ち出しが発生するため、可能な限り、入所時に持参された薬や市販薬で対応します。
こうした制度の壁の裏には、経営の苦しさがあります。
診療報酬(介護報酬)はなかなか上がらず、物価や人件費、光熱費は増す一方。多くの施設がギリギリの経営を強いられているのが現状です。
診療報酬を増やすには「ポイント稼ぎ」が必要?
収入を少しでも上げるには、国が定めた「加算」や「評価項目(ポイント)」を取る必要があります。
・新しい委員会を立ち上げる
・職員研修を増やす
・記録を細かくつける
・胃ろうや褥瘡ケアなど医療ニーズの高い人を受け入れる
…でもそれって、人手に余裕があれば、の話です。
常に人手不足の現場で、新たな取り組みに挑戦するのは簡単なことではありません。
制度に追われる中でも、大切にしたいこと
「点数を取るためにやる」のではなく、「利用者のためにやっていたら、結果的に点数がついてきた」――そんな運営が理想です。
現場には常に葛藤があります。
でも、それでも、一人でも多くの方が「家に帰れた」「笑顔が戻った」と言ってくださるように、今日も私たちは働いています。
老健という施設が、もっと正しく、多くの人に知られますように。
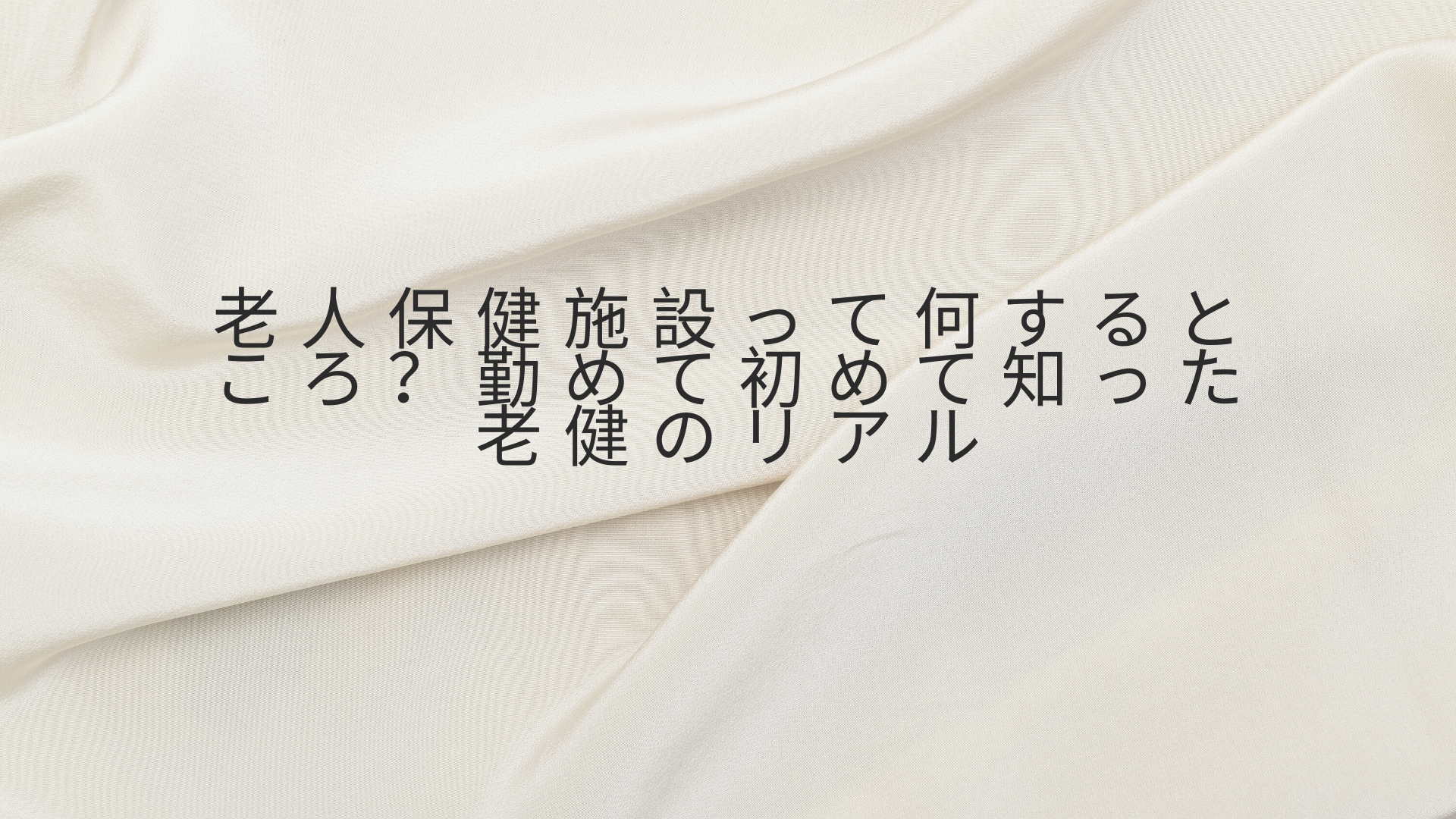

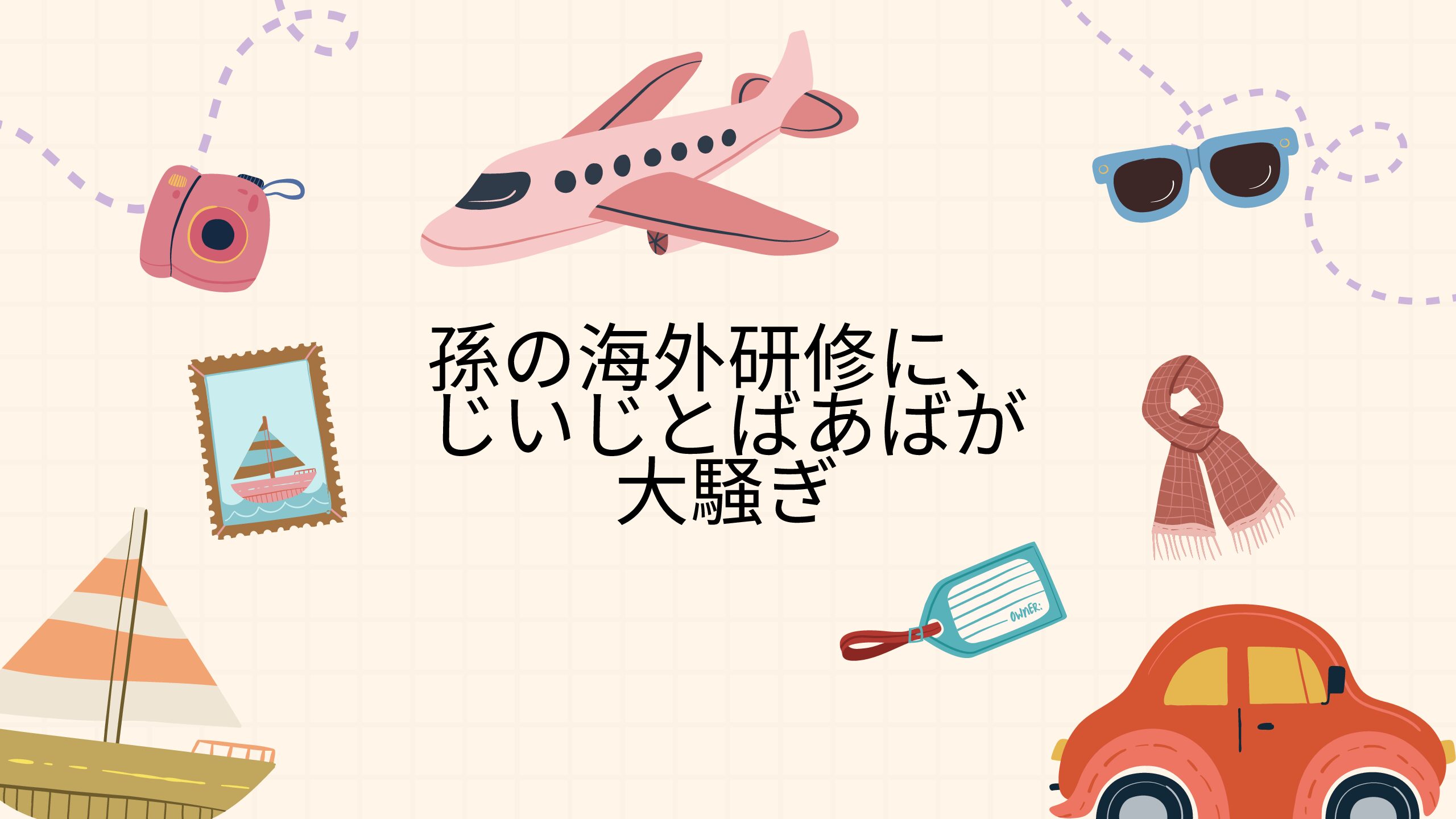
コメント