親の介護費用が月に数万円…。働き盛りの子ども世帯にとっては大きな負担ですよね。
実際、老健や特養の費用相談で「こんなに払えるのかしら…」と頭を抱えるご家族は多いです。
でも安心してください。
「高額介護サービス費」という制度を知っていれば、払いすぎた分は後からちゃんと戻ってくるんです。
高額介護サービス費とは?
介護保険サービスを利用したとき、利用者が支払う1〜3割の自己負担額には上限が決められています。
その上限を超えた分は「高額介護サービス費」として払い戻される仕組みです。
つまり、「介護にお金がかかりすぎるのでは…」という不安を和らげてくれる制度なんですね。
自己負担の上限額(1か月あたり)
上限額は世帯の所得状況によって決まります。以下は主な区分です。
| 区分 | 世帯の目安 | 上限額(月額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 課税所得145万円以上(年収約383万円〜) | 44,400円 |
| 一般 | 課税あり(上記以外) | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯(年金収入80万超〜約120万円以下) | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下) | 15,000円 |
※70歳未満の子世帯であっても、親が介護保険を利用している場合はこの区分に基づいて計算されます。
実際のケース:老健に入所した場合
例えば老健に入所し、1か月の介護サービス費の自己負担が80,000円になったとします。
利用者さんが「一般」の区分であれば、自己負担の上限は44,400円。
つまり、差額の35,600円が「高額介護サービス費」として後から戻ってきます。
これはご本人だけでなく、仕送りや費用を支える子ども世帯にとっても本当に助かる仕組みです。
世帯分離でさらに負担が軽くなることも
高額介護サービス費は「世帯ごと」に自己負担額の上限を判定します。
つまり、同居している子ども世帯の収入が高いと「現役並み所得」とみなされ、上限が高くなることもあるのです。
でも、住民票上で世帯分離をしておくと、親世帯は親自身の年金収入や預貯金で判定されます。
その結果、親世帯が非課税世帯に該当すれば、上限が大きく下がり、戻ってくるお金も増える可能性があります。
例えば、
- 同居&同一世帯 → 子どもの年収600万円 → 上限44,400円
- 世帯分離して親が年金収入のみ(非課税世帯) → 上限15,000円
と、同じ介護費でも大きな差が出ることがあります。
実際、我が家も「完全同居」ですが、住民票上は世帯分離をしているため、親世帯は非課税世帯として扱われています。
これによって介護費用の負担が軽くなり、子ども世帯にとっても大助かりです。
世帯分離には税や扶養控除などへの影響もあるため、実際に行う際には市区町村の窓口やケアマネジャーに相談してみてくださいね。
ただし、実際に市区町村に世帯分離の申請をする際には「生計を別にするため」と伝えることが重要です。ここで正直に「介護保険料を下げたい」と答えてしまうと、受理してもらえない場合があります。市区町村もここは分かっているので、上手くやるようにしてください。
申請の流れ
高額介護サービス費は、最初に一度全額を支払った後、
自治体から通知が届き、払い戻しを受ける仕組みです。
- 介護サービスを利用(まずは自己負担分を支払う)
- 自治体で利用料を集計
- 対象となる場合、翌月以降に通知が届く
- 指定口座に差額分が振り込まれる
※自治体によっては申請が必要な場合もあります。まずはケアマネジャーや役所に確認してみましょう。
まとめ:知識が子どもの家計を守る
介護費用は「払えるのかな…」と子ども世帯にとっても大問題。
でも、高額介護サービス費や世帯分離を上手に活用すれば、実際の負担は大きく抑えられるのです。
「制度を知っているかどうか」で、家計の安心度は大きく変わります。
ぜひ家族で話し合いながら、無理のない介護生活を考えてみてくださいね。
おすすめ書籍
- 両@リベ大学長の「本当の自由を手に入れる お金の大学」
介護費用の不安も含め、家計の守り方・増やし方を学べる定番の一冊。
👉関連記事:負担限度額認定(補足給付)について
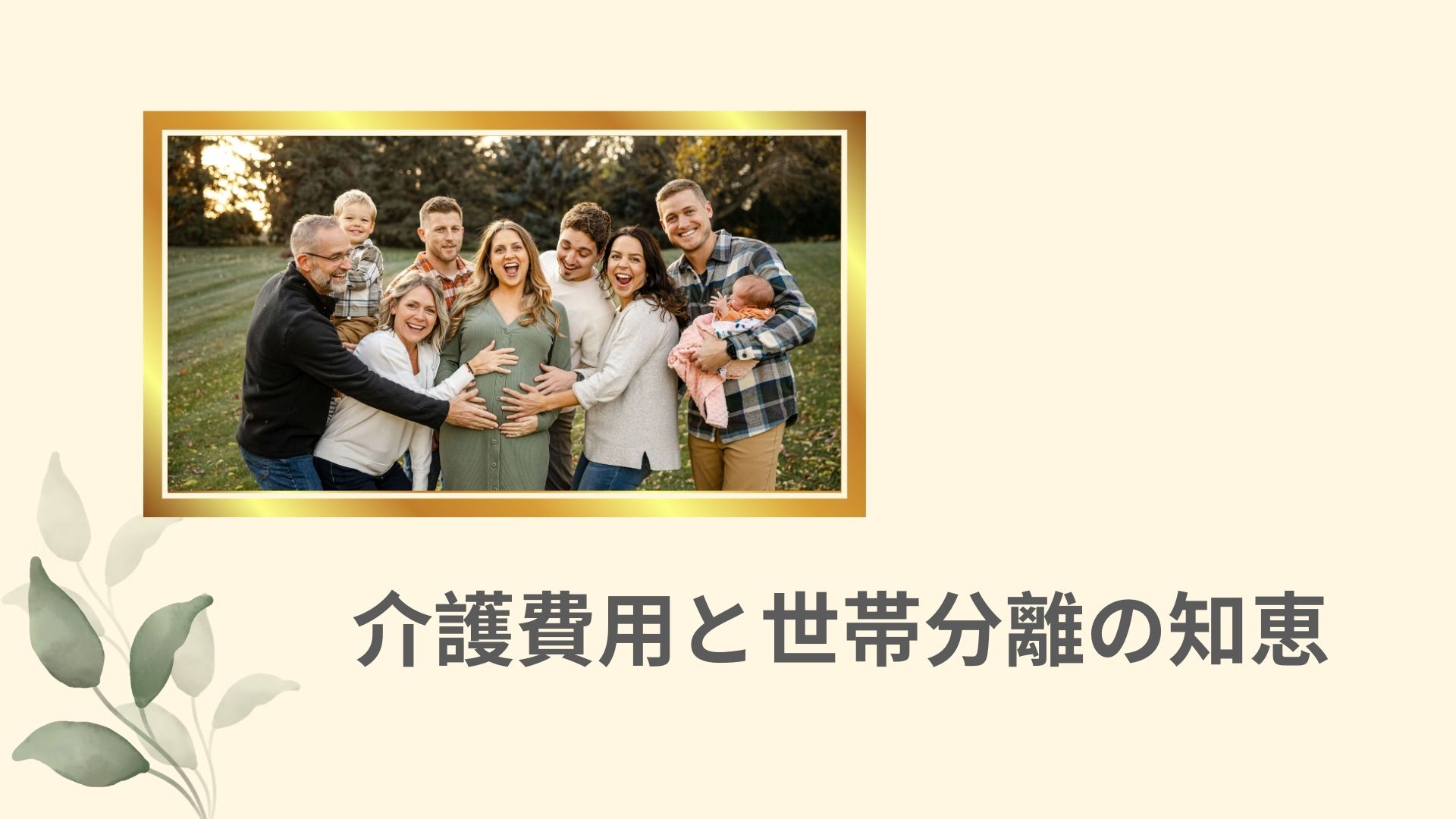


コメント