■ 入所者も利用者も、年齢が上がっている
最近、入所者の年齢がどんどん高くなっている。
90代は当たり前、100歳を超える方も珍しくなくなった。
当然、身体の機能も、感覚も、認知の状態も、ひと昔前とは違ってきている。
そして、介護する家族も年齢が高くなってきている。
「老老介護」や「認認介護」といった言葉が、現実のものとして目の前にある。
面会に来るご家族の足元がふらついていたり、「私も腰が悪くてね」と苦笑いされたり。
そんな姿を見るたびに、こちらが支えたくなるような気持ちになる。
■ デイケアを選ぶ人の顔ぶれが変わってきた
10年前、デイケアを希望する人の年齢は主に70代から80代だった。
でも今は、80代後半から90代がメインになっている。
100歳に近い方がリハビリに通うことも、もはや特別ではない。
一方で、70代の人たちはまだまだ元気だ。
カーブスやヨガ教室に通い、自分のペースで体を動かしている。
通所を選ぶとしても、半日型のデイサービスを利用して、
「リハビリ」よりも「気分転換」や「場」として活用している印象だ。
■ 「ここじゃないと対応できない」人が増えている
そう考えると、デイケアを選ぶ人たちはかなり限定的になってきている。
家族のリハビリへの意識が高いケース、
もしくは、集団プログラムでは対応できないような人が中心だ。
言い換えれば、「通えるから来る」ではなく、
「ここじゃないと対応できないから来る」——
そんな利用者層に変わってきているのを、現場ではひしひしと感じる。
■ 今、リハビリに求められるもの
そうなってくると、リハビリに求められるのは、専門性はもちろんのこと、家族へのフォローだ。
「本人のために」と思って通わせている家族も、
実際には「家での生活が成り立つかどうか」という切実な課題を抱えていることが多い。
介護する側も高齢だったり、身体に不調を抱えていたり、
精神的にも身体的にも、余裕がなくなっていることが少なくない。
だからこそ、ただ訓練を提供するだけでは足りない。
家の様子を聞き、生活動作の背景を想像し、
家族の「がんばりすぎ」に気づけるかどうか。
リハビリ職としての役割は、そんなところにもあるのではないかと思っている。
■ おわりに
利用者の年齢も、家族の状況も、時代とともに確実に変わってきている。
その中で、デイケアに求められる役割も進化している。
私たちは「通所リハビリ」という枠の中で、
もっと柔軟に、もっと深く、関わっていく必要があるのかもしれない。

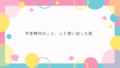
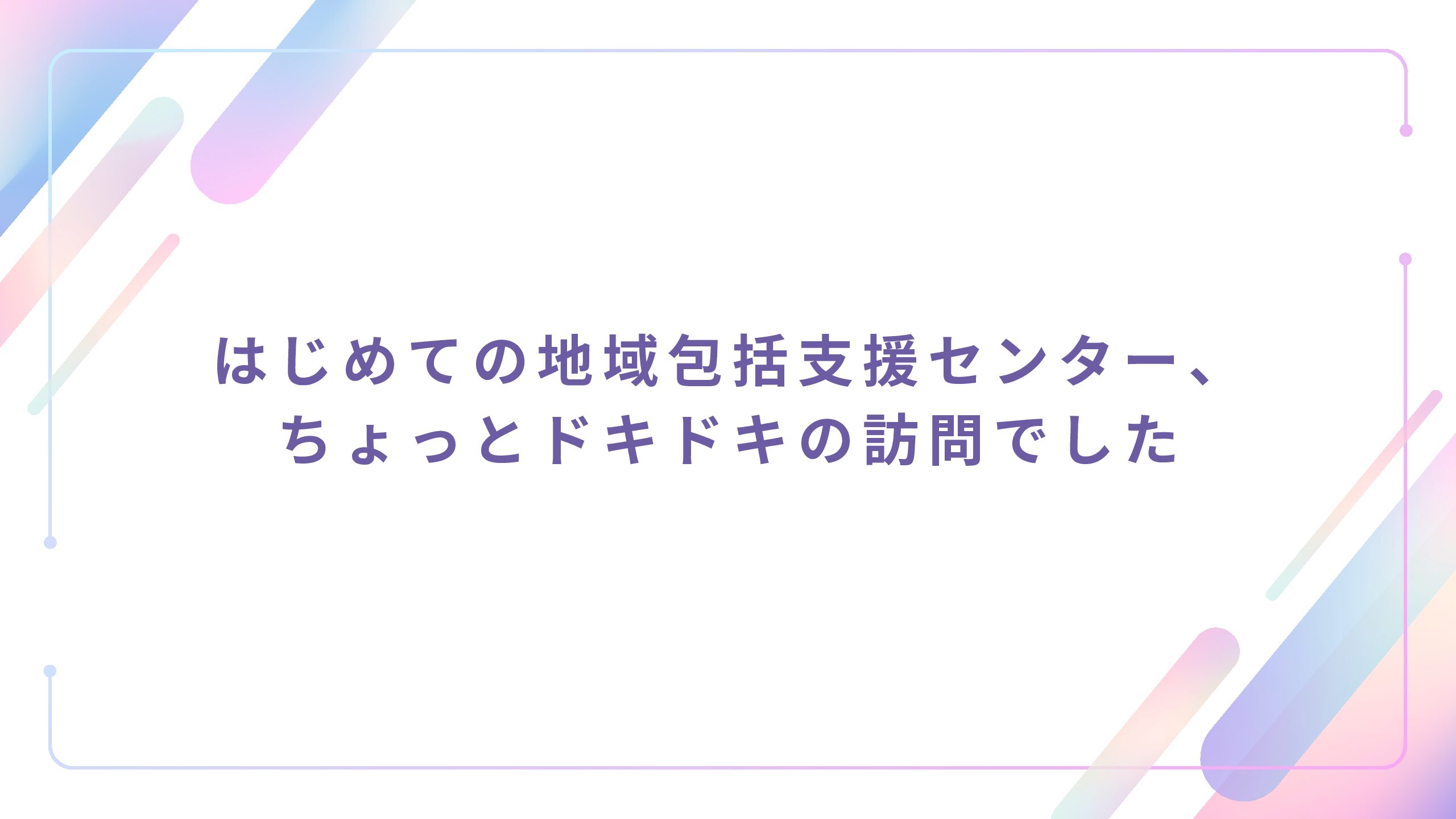
コメント